2025年5月3日の法話会と次回(6月3日)の案内
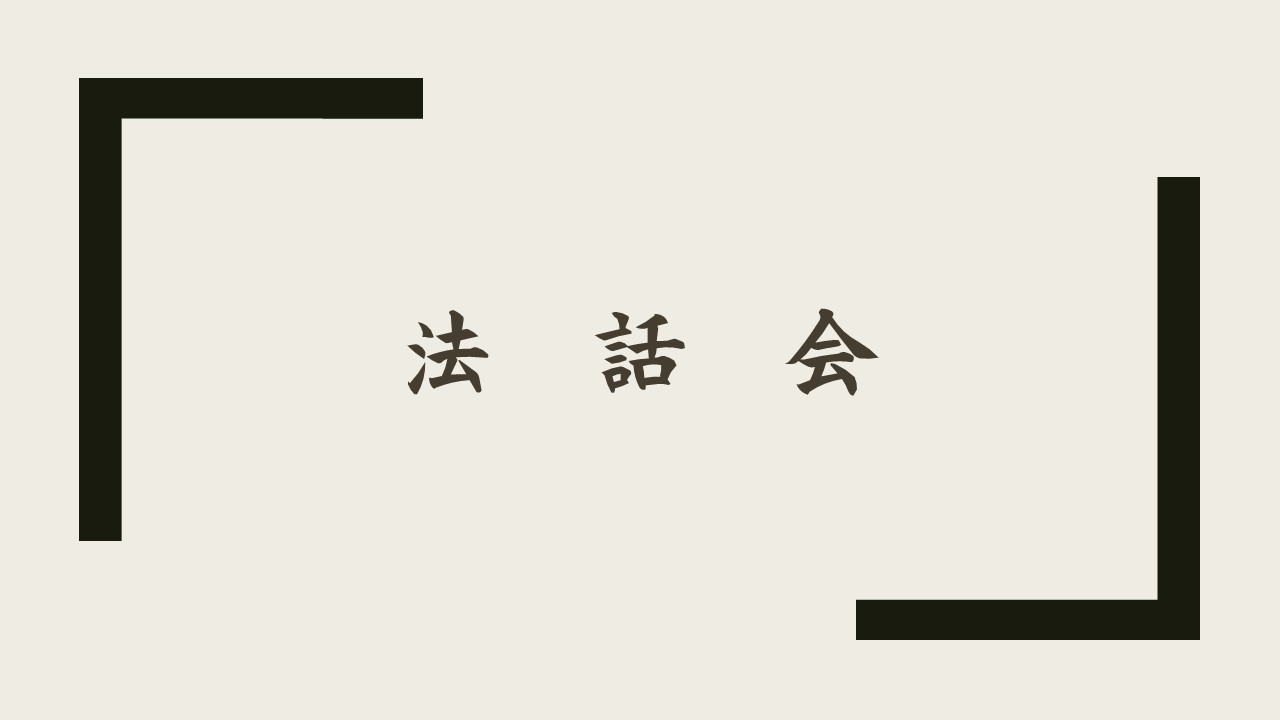
次回の法話会は、以下の日程で行いますのでどうぞお参りください。
(日時)6月3日(火)13時30分〜勤行後(30分)・法話(50分)
(講師)宗 秀融 師(福岡県)
─────────────────────
2025年5月3日(土)の永代経に、広島県より服部法紹先生がご出講くださいました。法話のないようをいくつか書き留めましたのでご紹介します(内容は概要です)。
Contents
命を締める一太刀―豊島に息づく食の作法
仏教において「殺生」は五戒の中でもとりわけ重い罪とされます。しかしながら、私たちは他の命を頂かなければ生きていけない存在でもあります。このジレンマを強く意識して暮らしているのが、瀬戸内海の小島・豊島の漁師たちです。
島の人びとは、魚介の命を奪わざるを得ない現実を受けとめつつ、「せめて苦痛を最小限に」という思いを行動で示しています。漁で獲った魚や貝は、必ず一太刀で締めてから調理し、生け造りのように生きたまま切り分けることは決してしません。沖合には魚の供養塔が建てられ、年に一度、漁師全員が寺の僧侶とともに読経し、永代経を勤めて命を弔います。こうした風習は、日常の営みと仏教的な「殺生」の教えとが折り合いをつける、島なりの倫理実践といえます。
その豊島に、人気絶頂期の料理人・道場六三郎氏がテレビ番組の収録で訪れました。漁師が差し出した生きたタコを氏が熱した鉄板へそのまま叩きつけ、苦しむ様子を気にも留めず手早く捌き始めた瞬間、見守っていた島民の表情は一変しました。普段は歓迎一色のはずの撮影現場に、ざわめきと沈黙が交錯し、小さく手を合わせて念仏を唱える者までいたと伝えられます。
同じタコを前にしても、島民にとってそれは「食材」である前に「ひとつの命」であり、敬意を払う対象です。道場氏が示した職人技は、都会の視聴者にとっては鮮やかな調理パフォーマンスかもしれません。しかし島の漁師たちには、「命をいただくならば、せめて無駄な苦痛を与えない」という暗黙の倫理に背く行為として映りました。
この出来事は、私たちが日々の食事でどれほど「いただく命」に自覚的でいられるかを問いかけます。生きるために殺生を避けられない現実を直視しつつ、相手の苦痛を減らし、感謝と供養を欠かさない──豊島の漁師たちの姿勢は、仏教が重視する「慈悲」と「懺悔」の実践例といえるでしょう。時折、私たちも彼らにならい、食卓に上る生命に思いを寄せる時間を持つことが求められているのではないでしょうか。
「両舌」の功罪―離間語が生む溝と橋
仏教における十悪の一つに「両舌」というものがあります。
「両舌(りょうぜつ)」です。現代語では「二枚舌」とも言われますが、両舌は嘘を意味するのではありません。辞書には「離間語」とも記されており、「こちらではこう説明し、あちらでは異なる説明をする」という行為を指します。
この説明を初めて聞いたとき、私は人と人とを仲違いさせるための手段を連想しました。しかし実際には、単に対立を生む目的に限らず、関係を円滑にするために用いられる場合もあります。たとえば私自身、僧侶であると同時に家庭の「中間管理職」の立場にあります。
結婚十二年目の私の家には、長崎出身の妻、三人の子ども、そして両親が同居しており、いわば二世帯同居です。妻は嫁という立場、母は姑という立場で、それぞれ気遣いながら円滑な関係を保とうとしています。しかし、表面上の努力だけでは済まされない場面もあります。
私は家族の「平和維持活動」を担う者として、両者の空気に微妙な違和感を覚えると、まず妻のもとへ赴き、「母はこう考えています」と伝えます。次に母のもとへ行き、「妻はこう感じています」と説明します。その結果、両者に対して異なる言い方をすることが避けられず、振り返れば「こちらとあちらで少し違うことを言っていた」という状況が生まれます。
この行為は両舌にあたり得ますが、目的は仲違いではありません。むしろ両者の関係を円滑にするため、やむを得ず離間語を用いる場合があるのです。皆さまも、職場や家庭で似たような経験をお持ちではないでしょうか。
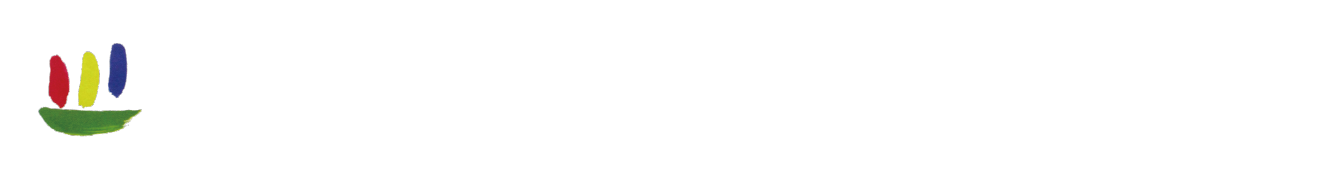
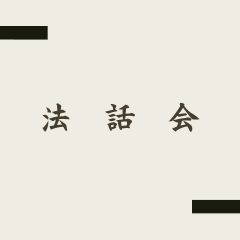

この記事へのコメントはありません。