2025年4月3日の法話会と次回(5月3日)の案内
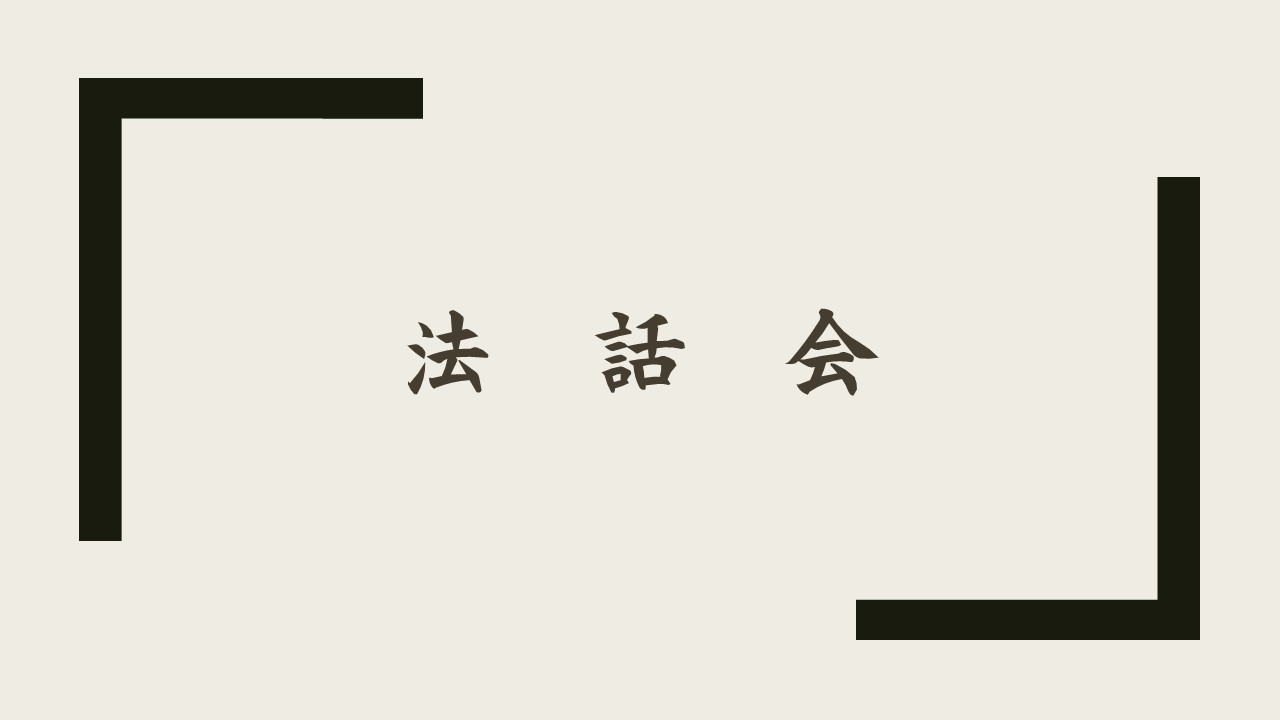
2025年4月3日(木)の法話会には広島県より中村啓誠先生がご出向くださいました。お話くださった内容の一部をご紹介します。
はじめに、次回の法話会は以下の日程で行いますので、どうぞお参りください。
(日時)5月3日(土)13時30分〜勤行後(30分)・法話(50分)
(講師)服部法紹 師(広島県)
Contents
浄土真宗は大人の宗教(趣意)
最初に唱えさせていただいたのは、宗祖・親鸞聖人が遺された『高僧和讃』の中の一首です。その冒頭に「本願力にあひぬれば」という言葉が出てきます。
「本願力」とは「本願の力」という意味であり、京都にある本願寺の「本願」もここから来ています。「根本の願い」という意味です。
大切なのは「誰の願いか」ということです。私たちはつい、お寺や神社に自分の願いを叶えてもらうために参るものだと思いがちです。
しかし、浄土真宗の教えでは、願いは私たちのものではなく、阿弥陀様の願いであると教えられています。阿弥陀様の願いとは、「命が終わったらそれでおしまいではない。浄土に生まれ、仏となって歩む人生を送ってほしい」というものです。
つまり、私たちを必ず浄土に往生させ、仏に仕上げてくださるという願いなのです。
その阿弥陀様の願いを聞かせていただく場所こそが、このお寺であると学びました。
一般的なお寺や神社では、私たちの願いを叶えてもらう場ですが、浄土真宗ではその向きが逆です。仏さまの願いを私たちが聞く宗教です。
私たちにもいろんな願いがありますが、突き詰めると「自分が幸せになりますように」という方向に収斂していくことが多いように思います。
私にも子どもが一人おり、配偶者も一人おります。その息子が小学生の頃、ガリガリ君というアイスが大好きでした。冷凍庫にはいつもガリガリ君が入っていて、息子は学校から帰ると手も洗わずに食べていました。私は「まず手を洗いなさい」と注意していました。
それでも彼は2本目、3本目と食べようとし、私は「ご飯の前にやめなさい」「お腹を壊すよ」と何度も言いましたが、案の定、後でお腹を壊しました。
息子の当時の願いは、「三度三度の食事の代わりに、三度三度ガリガリ君だけ食べて生きていけますように」というものだったと思います。
では、その願いをそのまま聞いて与える親は良い親でしょうか?そうではありません。
親である私の願いは、「この子が健やかに育つよう、正しい食習慣を身につけてほしい」というものでした。大切なのは親の願いの方だと思います。
浄土真宗は「大人の宗教」とも言われます。子どものような、愚かで一時的な願いに愛想よく付き合ってくれる宗教ではありません。
正面の阿弥陀様のことを「親様」とも呼びますが、親である阿弥陀様の願いを、私たちが聞かせていただく宗教なのです。
近くで見れば悲劇、遠くで見れば喜劇(趣意)
私の中には、今でも「許せない」と感じている相手がいます。それはかつての姑です。
けれども、その姑が亡くなり、何十年も経って、自分が姑と同じような立場になってみると、ようやく気づかされるのです。あの時の言葉は、私のことを思って、どうしても伝えねばならないという覚悟のもとに語ってくださったのではないかと。
当時は反発したその一言が、今となっては自分を支える大切な言葉になっていたことに、後になって気づくのです。
「あの一言があったから、今の私がある。お姑さん、ありがとうございました」と思えるようになるには、時を重ね、距離を置くことが必要なのかもしれません。
人生は、近くから見ると悲劇に見えても、引いて全体を見れば喜劇に変わるのです。
私が今日伝えたいのは、もし「自分の人生はむなしい」と感じている方がいたら、ぜひこの視点を持ってほしいということです。
それは、「クローズアップ(近距離)で見るのをやめて、ロングショット(遠距離)で見る」ことです。
自分の人生の意味を、自分の価値観だけで測ろうとすると、「勝ち組だった」「負け組だった」といった言葉が出てきてしまい、悲しい気持ちになることがあります。
そういう時こそ、阿弥陀様の目から見た自分の人生を想像してみてはいかがでしょうか。
阿弥陀様は、こう語ってくださっています。「あなたの人生はむなしいものではありません」と。
それは、私たちがご一緒に唱えさせていただいた「南無阿弥陀仏」というお念仏の中に、すでに響いている言葉です。
「あなたは死んだら終わり、そんな人生ではありません。命を終えたら、仏となり、すべての命の幸せを願って働く存在になるのです」と。
今、私たちはその尊い仏の子としての人生を歩んでいるのだと、胸を張って生きてください。南無阿弥陀仏には、そのような励ましが込められていると私は思っています。
そうして、お念仏とともに生きる人生には、もう「むなしさ」はなくなっているはずです。これこそが、浄土真宗における「ご利益」なのだと思います。
このご利益とは、生と死を貫いて、私たちに仏の子としての尊厳を与えてくださる、本当の命の支えです。今日、最初にご一緒に唱えた和讃には、そのことが表れていました。それは「命の宝」として、親鸞聖人が私たちに示してくださったものです。
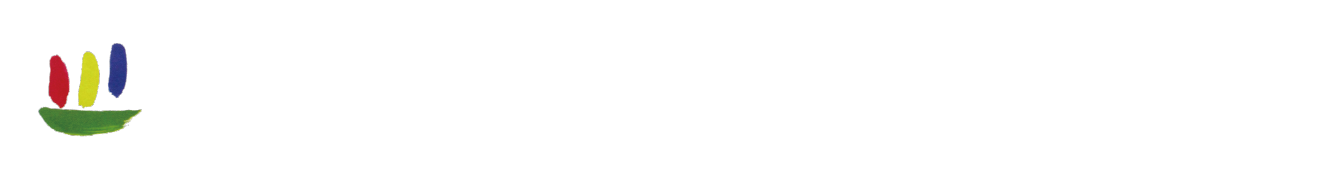
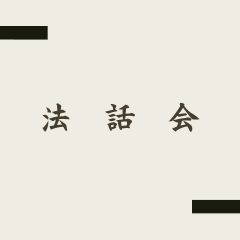
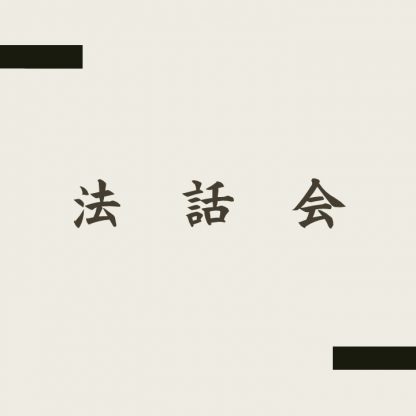


この記事へのコメントはありません。