2025年8月3日の法話会と次回(2025年9月3日)の法話会のご案内
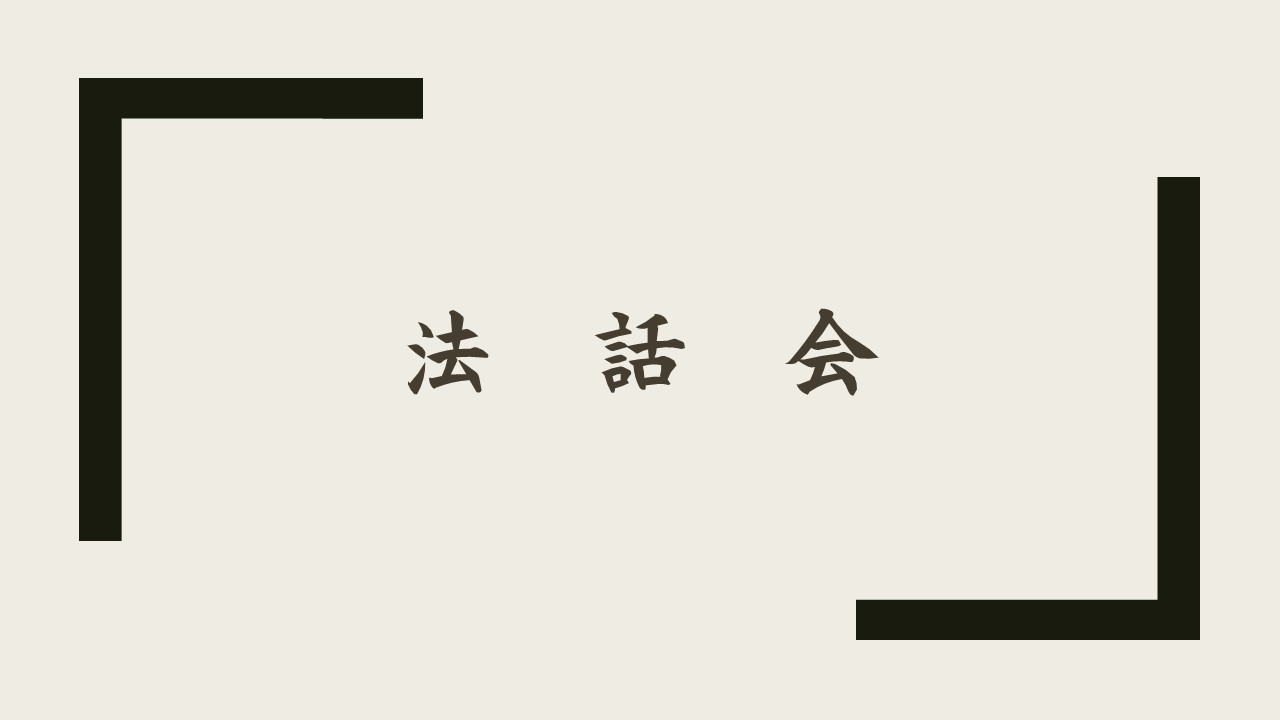
まず始めに次回の法話会のご案内をいたします。
(日時)2025年9月3日 13時30分~勤行/14時00分 頃~法話
(講師)紫藤常昭 師(福岡県)
(場所)西方寺・本堂
──────────────────────
2025年8月3日の法話会には、大阪府より若林眞人先生がご出講される予定でした。しかしながら、同年5月21日に急逝され、このたびは御子息である若林唯人先生が代わってご出講くださいました。
唯人先生は、浄土真宗というご法義が「むなしく終わっていく命」ではなく、阿弥陀さまに抱かれて仏とならせていただくみ教えであることを述べられました。それは「死んでいく命」ではなく、「阿弥陀如来の浄土に往き生まれていく命」であるという教えです。したがって、往生されることに対して「おめでとう」と申し上げることができる一方で、別れを経験する寂しさも否定せず、その相反する思いをともに包み込んでいく教えであると語られました。これらのお話は、ご自身のお父様のご逝去を通して深く実感されたものであったとのことです。
以下、その内容の一部をご紹介いたします。
──────────────────────
皆様、改めましてこんにちは。ただいまご紹介にあずかりました、若林唯人と申します。年齢は42歳です。本日は、皆様とご一緒に、阿弥陀さまのお慈悲の心についてお聞かせいただくご縁を頂戴いたしました。
仏教では、私たちの命を「蝋燭の灯火」に譬えることがあります。一度火が灯れば、必ずやがて消える時がまいります。最後まで静かに燃え尽きて消えていくこともあれば、まだ十分に残っているように見えても、ふとした風に吹かれて突然消えてしまうこともあります。私たちは、いつ命の灯が消えてもおかしくない存在であるということを、日々の中で知らされています。
。しかし、どれほど尊い命であっても、必ず終わりの時がやってまいります。そしてまた、大切な方々とも、必ず別れなければならない日が訪れます。
そのことを、私たちは頭では理解しているつもりでも、いざその現実を目の前に突きつけられたとき、果たしてそれを素直に受け入れることができるかと言えば、そう簡単ではありません。
仏教は、そのような私たちに向けて、「安らぎの道がある」と説いてくださる教えです。と申しますのも、仏教には大きく分けて二つの道があるとされています。先ほど皆様とご一緒にお勤めいたしました「正信偈」の中には、「顕示難行陸路苦、信楽易行水道楽」とありました。これは、インドの龍樹菩薩という方が説かれた「難行道」と「易行道」についてのお示しです。
「難行」とは、私たち自身が修行を重ね、煩悩を断ち、悟りに至るという困難な道です。この道を歩むには、まず「諸行無常」という仏教の根本的な真理を受け入れねばなりません。すべてのものは変化し続け、永遠にとどまるものはひとつもないという教えです。
そのような現実を直視し、それを当然のこととして平然と受け入れる境地に至った方こそが、「悟りを開いた人」であると言われます。しかし私たちには、そのような道を歩むことは、あまりにも困難です。
そこで、阿弥陀さまは私たちを見つめ、こう思案なさいました。「修行しなさい、悟りを開きなさい」と言っても、それができずに涙を流すばかりの私たちに、どうすれば安らぎを与えることができるだろうか、と。その深いご思案は、「正信偈」に「五劫思惟之摂受」とあるように、気の遠くなるような時間をかけて行われたと伝えられています。
その結果、阿弥陀さまは「私が修行し、私の力で全ての命をもれなく浄土に迎え入れる仏となろう」とお誓いになり、その誓いを実現すべく、長い修行を経て阿弥陀仏となられました。
その阿弥陀仏は、遠く離れた場所にいらっしゃるのではありません。命が尽きるその瞬間に迎えに来られるだけではなく、今この瞬間も、私たち一人ひとりと共にいてくださっています。
「阿弥陀」とは「無限の光」という意味で、その光は、どこまでも、誰にでも、今ここにも確かに届いています。そして生涯を通して、私たちの命を抱き支え、命終わる時には、必ずお浄土へと生まれさせてくださるのです。
そしてお浄土に生まれた私たちは、阿弥陀さまと同じ悟りを開いた仏さまとならせていただきます。その仏さまは、今度は残された命のもとへと還り来たり、導き、支えてくださる。まさに「救われる命」が、「救う命」へと変わる。そのような壮大な命のはたらきの物語が、浄土真宗の教えの核心なのです。
私がこのたび、阿弥陀さまのお救いを改めて深く味わわせていただいたのは、今年5月21日に、父が往生いたしましたことによります。
本来でしたら、このご法座において法話をさせていただくのは、私ではなく父でした。しかしながら、そのご縁が叶わず、代わって私がこの場に立たせていただくこととなりました。父は享年74歳、まだまだ若い年齢です。
父の体調に異変が現れたのは、4月の初め頃でした。肩や背中に痛みが出始め、当初は「肩こりがひどくなったのだろう」と思っていたようですが、その痛みは次第に神経痛のようなビリビリとした鋭いものになり、整形外科を受診することになりました。
最初に訪れたのは、近所のクリニックでした。医師からは「頸椎に原因があるかもしれない」とのことで、MRI検査を勧められました。検査を受けたのは4月21日で、その日の夕方に結果が返ってまいりました。ところが、首には異常はなく、「もっと下の方に原因があるようだ」と言われたのです。
それを父から聞いたとき、私は強い不安に襲われ、夜中にスマートフォンでいろいろと調べ始めました。そして目に飛び込んできたのは、「肺がんの末期」という言葉でした。父はタバコを吸う人でしたので、その可能性は十分にあると思い至り、そこからは眠れぬ夜を過ごしました。
それでも、今自分にできることは何かを考え、「残された時間を一日一日大切に過ごそう」と決意いたしました。翌日からは、毎晩、父とゆっくり話す時間を持つようにいたしました。私には当時3歳の息子がおり、18時頃に家族で夕食をとり、20時頃には寝かしつけてから、お寺にある本堂に向かいました。父はそこで一人お夕事のお勤めをしていましたので、その後、一緒に1時間、2時間と話す時間を過ごしました。
こうした時間を持てたことは、本当にありがたいことだったと今、振り返って感じています。
がんという病気は、もちろんつらく、残酷なものではあります。しかし、父のように余命をある程度覚悟した上で、その時間を共に過ごすことができたという点では、ある意味で「ありがたい病気」であったとも思えるのです。
医師からは「がん細胞にはいくつかの種類があり、進行の早いもの、遅いものがある」と説明を受けました。細胞の種類によって試せる治療法や薬の種類が異なり、検査によって詳しく調べることができるとのことでした。父はその説明を受けた上で、5月8日にがん細胞の検査を受けました。
しかしその頃には、父の痛みはさらに強くなっており、痛み止めの薬の量も増えてきました。
そして、5月17日・18日には、私どもの寺において永代経と春の法要が勤まりました。17日には昼と夜の二座、18日は昼座のみでした。
17日、父は「今日は体調がすぐれないので一日休ませてもらう」と言って寝ていました。翌18日の法話についても、「どうしようか」と悩んでいましたが、「最後になるかもしれないから頑張って話させてもらおう」と、気力を振り絞って立ち上がってくれたのです。
その日の法話で父がご讃題として掲げたのが、冒頭でご紹介した「本願力にあひぬれば…」の二首の御和讃でした。
これは、私たちが葬儀などで必ず拝読させていただく御和讃であり、まさに「死」と「往生」を語るにふさわしい御和讃です。父はその法話の中で、「皆様は、大切な方とのお別れをご経験されたことがあるでしょう。けれども今回は、命を終えていく本人が、その別れをどう受け止めているのか、そんな話をさせていただきたいと思います」と述べました。
その法話の中で、父は蓮の花のお話をしてくださいました。正面に立つ阿弥陀さまをご覧いただくと、蓮の花の台の上に立っておられる姿が見えます。蓮の花とは、仏教において仏さまの悟りを象徴する花で、蓮の花は、澄んだ地に根を下ろすのではなく、泥の中に根を張りながら、その泥に染まることなく、美しく咲く花です。
この花こそが、煩悩の中に生きる私たちが、そのまま仏の悟りに包まれて咲かせていただく花でありましょう。特に白い蓮華は、「一切善悪凡夫人 聞信如来弘誓願 仏言広大勝解者 是人名分陀利華」というお経の言葉にも示されるように、他力の念仏を聞き受けた私たちを、白蓮華にたとえてくださるものです。
父は、そんな蓮の花のお話を通して、「私たちは阿弥陀さまのお悟りの中に生まれ、仏さまとならせていただくのだ」と力強く語ってくれました。
父は、法話の中でさらに続けて語ってくれました。「如来浄華の聖衆は 正覚の華より化生して」というお言葉についてです。これは、インドの天親菩薩が『願生偈』という偈をおつくりになって、その中の「如来浄華衆 正覚華化生」という句に由来するものであり、後に漢訳されて「正覚華化生者」として伝えられた言葉です。
この御和讃は、「私たちは、阿弥陀さまがお悟りを開かれたその蓮の花に、生まれさせていただく」という教えを表しているものです。
父はこの言葉にふたつの味わい方があると話してくれました。一つは、『五会法事讃』などにある「念仏者がこの世に現れるたびに、極楽浄土に一輪の蓮の花が咲く」という解釈です。この世で念仏する人が現れると、浄土にその人のための蓮の花がひとつ咲く。まさに「予約席」のようなものだと、父は譬えていました。
しかしもう一つ、味わい方があるんですね。それは「この華は唯一無二の花である」という受け止め方です。親鸞聖人は『入出二文偈』にこのお言葉をお引きになって、「如来浄華の諸聖衆」と示されました。そして次に「法蔵正覚の華より化生す」と続くんです。これは法蔵菩薩の長きご修行の末に開かれた蓮の華のうえに生ずるという意味になるんですね。この華は一つしかありませんね。
そして、親鸞聖人は「如来浄華の衆 正覚の華より化生す」という御和讃の横にご自身で「浄華というは阿弥陀の仏になりたまひしときの華なり」とご自身で訓点を施されているんです。
つまり、私たちが往生する際に生まれさせていただく蓮の花とは、阿弥陀さまが仏となられたその時の「悟りの花」そのものであり、その尊き花に私たちは生まれさせていただくのだ、ということです。
これは何を意味するのかと申しますと、私たちは単に「浄土に行って終わり」なのではなく、阿弥陀さまと同じ悟りの仏さまに成らせていただくということです。
父は、法話の中でそのことを語ってくれました。「命を終えるということ、それは虚しいことではない。阿弥陀さまと同じ悟りを開いた仏とならせていただく。それがどれだけ尊く、楽しみなことか」と、目を輝かせて話してくれたのです。
しかしその翌日、5月19日の夜、父の呼吸が苦しくなり、夜10時ごろに「救急車を呼んでくれ」と申しました。私が駆けつけたとき、父の顔は青ざめ、汗を大量にかき、呼吸もままならない様子でした。すぐに救急車を呼び、搬送された先で医師から説明を受けました。
レントゲン写真には、わずか10日前と比べて肺の様子が一変し、白く濁った影が広がっていました。「これは間質性肺炎の進行によるもので、回復の見込みは厳しい」との説明でした。人工呼吸器の使用も検討されましたが、肺が酸素を取り込む力を失っており、苦しみを長引かせるだけになる可能性が高いとのことでした。
私は一人では決断できず、医師に「今、父と話ができますか」と尋ねたところ、「今はまだ安定しているので大丈夫です」と言われ、ICUに案内されました。
酸素マスクをつけながら、少し高いベッドに横たわる父に「お父さん、肺炎が進んでいて、治るのは難しいかもしれない」と伝えました。すると父は「そうか、そこまでやとは思ってなかった」と驚いた様子で応じました。
人工呼吸器の提案についても、「もうそこまではええわ」と静かに受け止め、「命を終えることが目の前に迫っていると聞いて、どう思うか」と私が尋ねると、父はしばらく考えて「楽しみや」と笑って答えました。
「この世に対して何か未練はないの?」と尋ねると、「それは特にないなあ」と言い、「こないだ法話で話したように、『浄華というは、阿弥陀の仏になりたまひしときの華なり』や。阿弥陀さまと同じ悟りの仏に成らせてもらえる。それが楽しみや」と、穏やかに語ってくれました。
それからしばらくして、母も病院に到着し、父と再会することができました。「お世話になりました。ありがとう」と感謝の言葉を交わし、少し冗談も言っていた父でしたが、5月21日の明け方、静かに息を引き取りました。
この日は、奇しくもがんの検査結果を聞きに行く予定の日でした。
お通夜、そしてご葬儀と、慌ただしく準備を進める中で、心に残る出来事がいくつもありました。
葬儀は、私たちの寺では収容しきれないご縁の方々が参列されることが予想されましたので、私も父も学ばせていただいた行信教校の広い講堂をお借りして執り行うこととなりました。
そのご法話をお勤めくださったのは、現在行信教校の校長先生を務めておられる天岸淨圓先生です。父とは、行信教校の学び舎において同時期に学ばれたご縁の深いお方です。
その天岸先生が、ご法話の冒頭において、父の棺の前に向き直り、静かに合掌・礼拝され、「若林さん、ご往生おめでとうございます」と語りかけてくださいました。
この「ご往生おめでとうございます」というお言葉は、浄土真宗の教えを体現するものとして、私の心に深く響いたものでした。
このお言葉には、前段となる背景がありました。かつて、私も父も教えを受けた勧学・梯實圓和上が、ご自身のご往生を見据えて次のように語られていたのです。
「わしが命を終えた後、『ああ、かわいそうに』とは言わんといてほしい。阿弥陀さまに抱かれて、浄土の仏さまにならせていただくんやから、かわいそうになるんと違うんや。どうか、『ご往生おめでとうございます』と言うてほしい」と。
天岸先生は、その言葉を心に深く受け止めておられ、梯和上の葬儀の際にも「和上、ご往生おめでとうございます」と語りかけてからご法話を始められました。今回、私の父の葬儀においても、まさにその時と同じように語ってくださったのです。
「ご往生おめでとうございます」。命を終えていく方に対して、見送る私たちがそう語りかけることができる。それは、本当にすばらしい教えに出会わせていただいた証であると、しみじみと感じた次第です。
命を終えるご本人が、「これからが楽しみ」と語ることができる。また、見送る私たちが「おめでとうございます」と手を合わせることができる。これほどまでに尊く、温かな教えがあることに、心から感謝の念が湧いてまいります。
その後、もう一つ、うれしいご縁がありました。それは、来月このご法座にお越しくださるご予定の、紫藤常昭先生とのつながりです。
父は毎年、山口県の俵山温泉で開催される勉強会「俵山安居」に参加していました。そこは、深川倫雄和上という勧学が主宰されていた学びの場であり、紫藤先生も若い頃からずっと共に学ばれていたお仲間でした。
父の葬儀にはご都合がつかず、紫藤先生は参列できなかったのですが、一筆箋に短いお手紙を添えて、お香典を送ってくださいました。そのお手紙には、次のように記されていました。
「前略 このたびの若林さんご逝去のこと、衷心よりお悔やみ申し上げます。常に意識し、目標にしてきた偉大なる先輩でした。残念でなりません。今も楽しかった昔の日々を思い出しては反芻しております。残念ながら通夜も葬儀にも出席できません。わずかばかりですが、お香典を送りますので、ご仏前にお供えくださいませ。称名 南無阿弥陀仏」
このお手紙を拝見したとき、私の胸にもこみ上げるものがありました。紫藤先生のような布教使として尊敬されているお方が、父のことを「目標としてきた」とおっしゃってくださる。それは、子として誇らしく、うれしいことでした。
そして、6月の俵山安居に、私も二日間だけ参加させていただきました。夜、少しお酒をいただきながら、紫藤先生に「お手紙をありがとうございました」とお礼を申し上げると、先生はこう話してくださいました。
「いや、実はあの手紙、悩んだんや。浄土真宗では、『命を終える』ことを『死』とは言わずに『往生』と言います。往生と書くと、次には『おめでとうございます』と続けたくなる。でも、今回はそれが言えなかった。本当に残念で、悲しくて、寂しくて…。だから、どうしても『ご往生』と書けず、『ご逝去』と書かせてもらったんや」
このように言葉を選びながら、深い思いを込めてくださったことが、何よりもうれしく、また浄土真宗の教えの奥行きの深さを改めて知らされるご縁となりました。
紫藤先生とのその会話の中で、私が思い出したのは、三重県の伊賀地方でおこなわれているあるご葬儀の習慣です。そこでは、葬儀にお集まりになった方々に「お赤飯」と「唐辛子汁」がふるまわれるという風習があるそうです。
お赤飯は、「命を終えた方は、今や仏さまとなられたのだから、めでたいことである」という意味が込められています。しかし、唐辛子汁のほうは、少し飲んだだけでも涙が出るほど辛いものです。「往生はめでたいことではあるけれども、それでも、別れはやはり悲しい。寂しい」。その両方の心が、共にそこにあるということを、この二つの食べ物に象徴させているのだと伺いました。
このことを思いますと、「ご往生おめでとうございます」と申し上げると同時に、「寂しい、悲しい」と思う心もまた、けっして否定されるものではなく、両方の思いが許されているのが浄土真宗の教えの深さであると感じさせていただくのです。
その後、先月の9日には、満中陰のご法事をおつとめさせていただき、一つの区切りを迎えたのですが、やはりまだ現実としての実感が心に追いつかないという日々を過ごしています。
たとえば、自宅の玄関のドアが「パタン」と閉まる音が聞こえると、「あ、お父さんが帰ってきたのかな」と、つい思ってしまいます。リビングのソファーに目をやると、いつも父があぐらをかいて、膝に猫を乗せて撫でていたその姿が浮かんできます。しかし、今そこには猫だけがぽつんと座っていて、少し寂しそうな表情を見せています。
また、お寺の本堂に近づくと、かつて聞こえていた父のお朝事やお夕事の読経の声が、今にも聞こえてきそうな気がします。しかし、いざ本堂に入ってみると、しんと静まり返っており、正面に飾られた父の遺影と遺骨を前に、「ああ、やっぱりもういないんだなあ」という現実を突きつけられます。
そのとき、心は沈んでいきますが、もう少し顔を上げて、阿弥陀さまの御尊顔を仰がせていただきますと、ふと心が穏やかになるのです。
「父は死んでしまったのではない。阿弥陀さまの蓮の花のうてなに生まれさせていただき、仏さまとなられたのだ。今もなお、この場に帰り来て、私たちを見守り、支えてくれているのだ」と思うとき、心があたたかく、力強くなってまいります。
阿弥陀さまは「無限の光」であるとともに、「無限の命」でもあります。その光と命に包まれた父は、今や阿弥陀さまと同じ悟りの仏となられ、またこの場に帰り来ておられるのだ。そう思うと、「南無阿弥陀仏」とお念仏するたびに、「ここにいてくださる」という確かな感覚が湧いてまいります。
この法話も、きっと一緒に聞いてくれていることでしょう。「そろそろ時間やで」と、いつものように注意されるかもしれませんが、それすらも懐かしく、ありがたいことです。
本当に、この阿弥陀さまの救い、お念仏の教えに出遇わせていただいて、よかったと思います。これからも同じように、この救いを引き受けながら、支えられながら、同じ浄土に生まれさせていただき、阿弥陀さまと同じ悟りの仏さまとならせていただく。そのことを念じながら、日々を大切に生きてまいりたいと思っています。
阿弥陀仏という仏さまは、今ここにご一緒くださっています。「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と私たちが声に出して称えるその場に、常にいてくださる。そういう仏さまです。
そして、父もまた、同じ仏さまとなられ、今この場に帰り来て、これからの私の歩みを、皆さまの歩みを、静かに支え続けてくださることと思います。
皆様にも、きっとそれぞれに、大切なお方とのお別れのご縁があったことと思います。その方々も、父と同じように、「南無阿弥陀仏」のお心に抱かれて、浄土に生まれさせていただき、仏さまとなられていることでしょう。そして、今この場に帰り来て、私たちと共にいてくださるにちがいありません。
阿弥陀さま、そして先に往かれた大切な方々、仏となられた皆さまに、私たちは人生を支えられながら生きている。そして、いつか必ずこの命が尽きるとき、私たちもまた、同じように浄土に生まれさせていただき、仏とならせていただく。そして再びこの世に還り来たり、残された命を導き、支えていくはたらきをさせていただくのだ――。
このような壮大な、しかし決して絵空事ではない、確かな命のはたらきを教えてくださるのが、浄土真宗のお救いです。
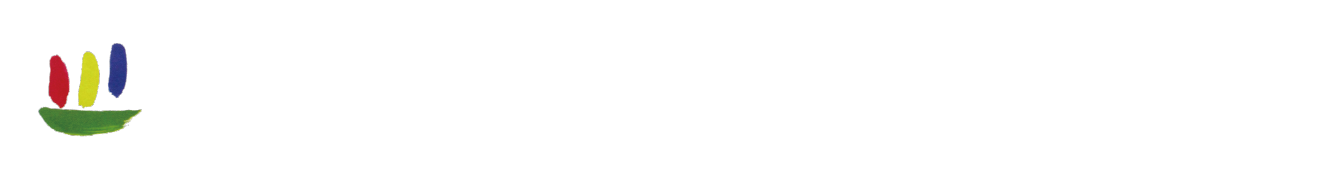
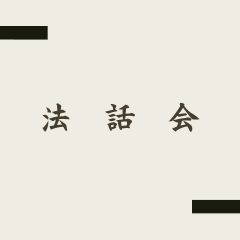
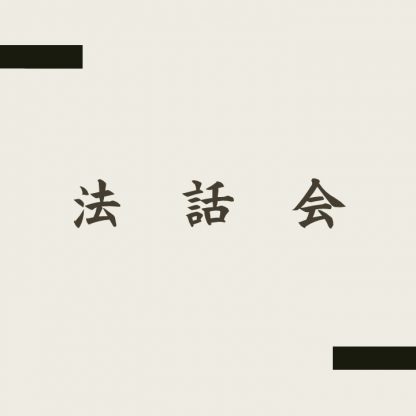

この記事へのコメントはありません。